こんにちは、佐々木優です。IT企業を経営している私ですが、今日は少し違うテーマでお話しさせてください。
先日、ある音声データを聞く機会がありました。それは被爆者の田中熙巳(てるみ)さんの証言でした。私たちの世代は戦争を知りません。でも、この証言を聞いて、「知らない」ではすまされないと痛感したんです。
トランペットの音に込められた願い
音声の冒頭で流れるトランペットの厳かな音色。そこに込められた願いは「人類が核兵器で自滅することのないよう、そして核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて、共に頑張りましょう」というものでした。
正直、最初は「また平和の話か」と思ってしまった自分がいます。でも、この言葉の背景にある物語を知ったとき、私の中で何かが変わりました。これは単なる理想論じゃない。血と涙と、そして人間の尊厳をかけた闘いから生まれた言葉なんだと。
13歳の少年が見た地獄
運命の8月9日
田中さんは1945年8月9日、まだ13歳の中学1年生でした。戦争の激化で学校はほとんど機能していない。その日も朝から空襲警報が鳴り響いていたそうです。
彼は自宅の2階で本を読んでいました。ふと、B29の音が聞こえる。でも、たった1機。「これで爆撃はないだろう」と高を括った、まさにその瞬間でした。
世界が真っ白に染まったんです。
何が起きたか理解する間もなく、本能的な危険を感じて1階へ駆け下り、目と耳を塞いで伏せた。そこで記憶が途切れます。
次に意識が戻ったとき、必死に彼の名を呼ぶ母の声が聞こえました。気がつくと、大きなガラスの下にいた。不思議なことに、そのガラスは一枚も割れておらず、奇跡的に無傷で助かったんです。
一歩外に出ると、そこは地獄だった
でも本当の恐怖はここからでした。
外に出ると、町の人々が「自分の家に爆弾が落ちた」と叫びながら、血を流して防空壕へ逃げ惑っている。田中さんも2人の妹を連れて防空壕に向かいました。
私はここで想像してしまうんです。13歳の少年が、幼い妹たちの手を引いて、血まみれの人々の中を必死に走る姿を。きっと怖かったでしょう。でも、お兄ちゃんとして妹を守らなければという責任感もあったはず。
3日後の絶望
本当の地獄を目の当たりにしたのは、それから3日後のことでした。
爆心地近くに住む2人の叔母の安否確認のため、田中さんは惨状が広がる市街地に足を踏み入れます。かつて家々が軒を連ねていた場所は、3キロ先の港まで見通せるほどのがれきの野原になっていました。
焼けた家の中には黒焦げの死体が転がり、道端では大火傷を負った人々が誰の助けも得られないまま苦しんでいる。爆心地からわずか400メートルの場所に住んでいた叔母とその孫は、真っ黒焦げの遺体となって発見されました。
もう一人の叔母は大火傷を負い、田中さんたちが到着する直前に息を引き取っていた。
変わり果てた親族の姿を見ても、涙は出なかったそうです。「何の感動もわかない」。あまりに非現実的な光景は、13歳の少年の感情を麻痺させていました。
たった一発の爆弾で、彼の親族5人の命が奪われたんです。
この部分を読んでいるとき、私は胸が詰まりました。ITの世界で働く私たちは、データの消失や破損について日々気を遣っています。でも、人の命は復元できない。一度失われたら、もう二度と戻ってこないんです。
7年間の沈黙 – 語ることすら許されなかった被爆者たち
戦後、被爆者たちにはさらなる苦しみが待ち受けていました。これは私も知らなかったのですが、アメリカ占領軍によるプレスコード(言論統制)により、原爆の被害について語ることが7年間も固く禁じられていたんです。
7年間ですよ。放射線という見えない敵がもたらす病に苦しみながらも、その苦しみを誰にも話せない。社会からの理解や援助もなく、彼らは孤立無援のまま耐え忍ぶしかありませんでした。
私たちの業界では「情報の透明性」を重視します。でも当時の被爆者は、自分たちの体験すら口にできなかった。どれほど辛かったでしょうか。
沈黙を破った転機 – 第五福竜丸事件
転機が訪れたのは1954年の第五福竜丸事件でした。アメリカの水爆実験により、日本のマグロ漁船が被曝したこの事件は、広島・長崎以外の人々に初めて核の恐ろしさを実感させました。
これをきっかけに、全国で原水爆禁止を求める国民運動が燃え広がったんです。
このうねりの中で、全国に散らばっていた被爆者たちが立ち上がりました。「力を合わせて自分たちの苦しい立場を解決しよう」と。
日本被団協の結成 – 団結の力
1956年、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が結成されます。彼らは国に対して粘り強く援護を求め続けました。
その結果、被爆から12年後、ついに被爆者健康手帳が交付され、国による援護への道が開かれたんです。その後も運動は続き、医療費の自己負担分が無料になる特別被爆者制度など、少しずつ援護策が拡充されていきました。
私はここで、スタートアップ企業の成長過程を思い浮かべました。最初はたった一人から始まって、同じ志を持つ仲間が集まり、社会に変革をもたらしていく。被爆者の方々の闘いも、まさにそういうものだったんじゃないでしょうか。
ただし、この場合は自分たちの利益のためじゃない。未来の人々が同じ苦しみを味わわないようにという、純粋な想いからの行動でした。
現代への問いかけ – 高校生との対話
物語は現代へと繋がります。ある集会で、高校生が田中さんに問いかけました。
「どうすれば興味のない人や知らない人にも、戦争というものを広められますか?」
この質問、すごく現実的だと思いませんか?私たちIT業界でも、「どうすれば新しい技術に興味を持ってもらえるか」「どうすれば社会課題を自分事として捉えてもらえるか」という同じような悩みを抱えています。
田中さんは静かに、しかし力強く語り始めます。
「戦争は、まさに殺人道具を作って喧嘩するようなものだ」
そして、戦争を望み、それによって利益を得るのはごく一部の人間であり、多くの人々は戦争を望んでいないと指摘したんです。
「誰が何を言っているのか、よく見極めなければならない」
情報に惑わされず、物事の本質を見抜くことの重要性を説いた言葉です。
これって、私たちがネット社会で生きる上でも本当に大切なことですよね。フェイクニュースが横行し、様々な思惑を持った情報が飛び交う中で、「誰が何を言っているのか」を見極める力は必須です。
まだ山積する課題 – 被爆二世の現実
しかし、課題はまだ山積しています。被爆者の親から生まれた「被爆二世」は、親と同様の健康不安を抱えながらも、法的な援護の対象外なんです。
田中さんのもとには、今なお「母親が被爆二世で苦しんでいるが、何の保証もないのか」といった悲痛な相談が寄せられるそうです。
ロシアによる核の威嚇が現実のものとなり、核のタブーが壊されようとしている今、田中さんの言葉は一層の重みを持っています。
私は仕事柄、システムの「継承」について考えることが多いのですが、被爆の影響は世代を超えて続いているんですね。しかも、技術的な継承と違って、これは人間の命と健康に直結する問題です。
最も伝えたいメッセージ – 「継承ではなく、実行を」
物語の最後に、田中さんが最も伝えたいメッセージを口にします。
「継承してほしいのではない。核兵器をなくすことを実行してほしい」
この言葉を聞いたとき、私は衝撃を受けました。
過去の悲劇をただ語り継ぐだけでは不十分だという痛切な叫び。被爆者の苦しみを本当に理解するならば、同じ過ちを繰り返さないために、核兵器廃絶という具体的な行動を起こしてほしい——。
私たちIT業界では「レガシーシステム」という言葉があります。古いシステムを維持し続けることの難しさや危険性について、日々議論しています。でも田中さんの言葉は、それとは真逆でした。
「過去を保存するだけじゃダメ。未来に向けて行動しろ」
これは私たち一人ひとりへの、重く、そして希望に満ちた宿題なんです。
私たちにできること
この音声データを聞いて、私は自分に問いかけました。「私に何ができるだろう?」
ITの力で平和に貢献できることはないか。核兵器廃絶に向けて、技術者として、経営者として、一人の人間として、何ができるだろうか。
答えはまだ見つかっていません。でも、少なくとも知ることから始めよう。そして、知ったことを周りの人に伝えよう。そう決めました。
皆さんも、もしよろしければ、この田中さんの言葉について考えてみてください。「継承ではなく、実行を」という言葉の意味を。
この物語の見どころ
最後に、この音声データで特に印象的だった4つのポイントをお伝えします。
1. 田中熙巳さんの生々しい被爆証言
13歳の少年が体験した原爆投下の瞬間、奇跡的に助かった直後の混乱、そして3日後に目の当たりにした爆心地の地獄のような光景。
特に、親族の遺体を見ても「何の感動もわかない」と語る部分には、戦争が人間の感情すら破壊する非情さが凝縮されています。私は何度も音声を止めて、深呼吸しなければなりませんでした。
2. 沈黙から行動へ – 被爆者運動のダイナミズム
戦後7年間、プレスコードによって被害を語ることすら許されなかった被爆者たちが、第五福竜丸事件をきっかけに団結し、日本被団協を結成していく歴史的プロセス。
個人の悲劇が社会を動かす大きな運動へと昇華していく様子は、本当に力強いものでした。私たちも、一人では小さな存在でも、同じ志を持つ人々と手を取り合えば、社会を変えられるんだと希望を感じました。
3. 未来世代との対話
高校生からの「どうすれば戦争を広められるか?」という真摯な問いに、田中さんが自身の経験と洞察をもって答える場面。
戦争の本質を「殺人道具を使った喧嘩」と喝破し、戦争を望む人々の構造を鋭く指摘する言葉は、世代を超えて響く普遍的なメッセージでした。
4. 「継承ではなく、実行を」という魂のメッセージ
この音声データのクライマックス。被爆体験を「語り継ぐ」だけで終わらせるのではなく、その悲劇を知った者が「核兵器をなくすことを実行する」責任があるという力強い訴え。
これは単なる過去の記録ではなく、未来への行動を求める力強い呼びかけなんです。私は、これからの人生で何度もこの言葉を思い出すことになるでしょう。
長い文章を最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
田中熙巳さんの言葉は、私たち一人ひとりに向けられています。技術者として、経営者として、そして何より一人の人間として、この言葉の重みを胸に刻んで、これからの人生を歩んでいこうと思います。
核兵器のない世界。それは決して夢物語ではなく、私たちの行動次第で実現可能な未来なのかもしれません。
参考番組:NHKアカデミア 田中熙巳(前編)“被爆者のために”戦い続ける
この記事について
執筆者:佐々木 優
→ プロフィール詳細
企画・取材:miku
→ プロフィール詳細
この記事は、ITコンサルティングを専門とする 株式会社リミブレイク が運営するメディアとして、独自の取材と分析に基づき制作されました。
#核兵器廃絶 #被爆者の声 #平和への願い #戦争を語る #継承から実行へ #核なき世界


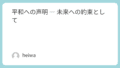

コメント